|
【コメント】 ポール・マッカートニーの曲の聴きどころ、調整しどころ。ポイントは「人間性」。 ポール・マッカートニーが個人的に好きなジャズを楽しんで歌う。ロックの大スターが、心から好きなジャズを楽しく奏でるという、アットホームで、CHEERFULな雰囲気が車室で再現、エンジョイできるか。 まず、冒頭のスネアドラムの軽快なブラシのスイング感、ウッドベースのつま弾きの伸びとストップのレスポンス。 ワンフレーズごとに編成が変わる、ギターとピアノの合奏で、各楽器の音色、質感が出るか。 ポール・マッカートニーの声は優しい歌い回しで、暖かい感情が籠もっている。軽妙な歌い方に籠めたポールのジャズへの思い、豊かな人間性が聴けるか。 音作りではそんなヴォーカルの質感、感情のニュアンスを出したい。単にオーディオ的な音の良さだけでなく、感情と音楽性をいかに表現できるかの力が試される。静謐なジャズヴォーカルの再現という、新しい次元の音づくりに挑戦しよう。オンマイクの音像は大きい、あまり締めすぎず、緩めすぎず。 歌詞の分析も大切。歌詞の内容が実際のスピーカーからの声ではどう表現されるか。 1:20のピアノソロの鍵盤のタッチ感、音の転がり感、スイング感のリアルな再現もポイントだ。 ヴォーカリストの人間性を感じさせる音を表現したい。 |
||||
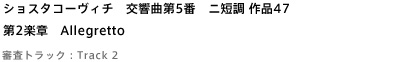 |
||||
| 【コメント】 2011年5月、佐渡裕がベルリン・フィルに初めて客演指揮したときのライブ盤です。小学生のころからの夢がかなったのですから、熱演になるのは当然です。 その一方で、この次に呼ばれるかどうかは結果次第。オーケストラの意向次第。そんな一発勝負の状況で、よくベルリン・フィルを本気にさせたと感動です。 東日本大震災の直後でもあり、彼には特別な想いがあったでしょう。 ショスタコーヴィチについては「二重言語」という表現がよく使われます。 スターリン独裁体制の下、身の危険を回避するために外面的には旧ソ連当局が気に入るような表現をとりながら、その中に自らの主張を巧みに潜り込ませた、という意味に解釈していいでしょう。どちらが真の姿なのだろうか。その生き方や芸術に対する評価も二分されてきました。多くの芸術家が自由な表現を求めて闘い、また亡命する中で、ショスタコーヴィチは「社会主義リアリズム」による統制下で芸術活動を行う道を選んだのは何故だろうか。その背景や理由を考えるのは大切なことでしょう。 1934年に初演されたオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」は、テーマも音楽もきわめてセンセーショナルなもので、ショスタコーヴィチの作曲家としての地位は揺るぎないものになったかに見えました。ところが1936年にスターリンがこのオペラを見て激怒し、途中で退席。共産党の機関紙「プラウダ」に痛烈な批判が掲載されました。作曲家としての地位を危うくするだけでなく、体制への反逆者として生命の危険すら覚悟しなければならない事態になったのです。 そこで翌年発表されたのが交響曲第5番です。この作品は、まさに起死回生の一発となりました。当局は、これを絶賛。 とくに第4楽章は社会主義リアリズムの勝利を賛美する音楽とされたのです。それがショスタコーヴィチの本意であったかどうか。様々な解釈が行われていますが、真実はわかりません。 さて課題の第2楽章ですが、これはスケルツォとなっています。スケルツォとは本来イタリア語で「冗談」といった意味ですが、日本では諧謔などと訳されることもあります。要するに「笑い」「ユーモア」「ウィット」などのことですが、この作品には「風刺」、あるいは体制への「あざけり」や、体制や大衆へ迎合せざるを得ない「自嘲」があるかもしれません。 冒頭はチェロとコントラバスが同じ旋律を奏でます。ここは別々の楽器ではなくチェロ+コンバスが一つの楽器のように響くべきです。重く太い鳴りのチェロです。重苦しい時代の足音でしょうか。やがてホルンのリズムが加わりますが、それを打ち消そうとするかのように自己表現を求める叫びが木管楽器によって奏でられます。この音色は鮮烈ですが、すぐにクラリネット1本になり、その声は孤独です。木管合奏やファゴットが孤独な闘いを引き継ぎ、やがて弦楽合奏も加わります。しかし、その間ずっとリズムを刻んできた足音に勢いが出て金管の強奏……叫びは体制を象徴する行進曲によって威圧され、押しつぶされていくのです。 ベルリン・フィルハーモニーのホールは響きの飛びが良いことで知られています。残響がスーッと抜けるように広がっていきます。頭が押しつけられるような響きではありません。この空間表現は大切です。各パートもクリアな録音ですが、あくまでオーケストラ全体が作り出すステレオイメージを重視してほしいと思います。そうすれば個々の楽器の位置は自ずと定位し、奥行きも出ます。 さらに弦楽器群の圧倒的な合奏力。強靱さ、勢い、強弱の妙味など、再生周波数のエネルギーバランスがとれていないと再現できません。とくに中低域の明瞭で厚みのある表現は必須です。管楽器の音色にも気を遣ってほしい。光と影が交錯する表現が、この演奏の醍醐味だからです。理不尽で荒々しい狂躁の影で埋もれてしまいそうな孤独で微細な声。哀しくもあり、弱々しくもあり、それでも生き続ける……。そこに作曲者の意図を感じてほしいと思います。 |
||||






