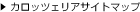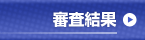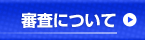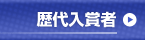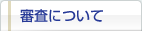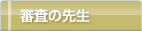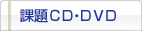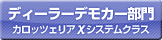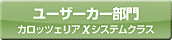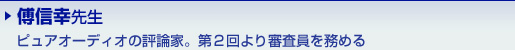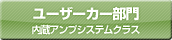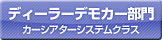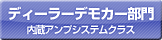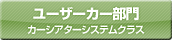本サイトはスタイルシートを使用しております。
お客様がご使用のブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
第12回カーサウンドコンテスト > 審査について
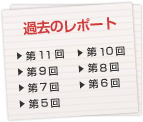
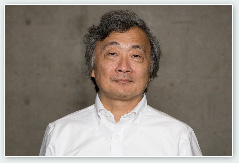
今年も、たいへん得点の拮抗した、かなりの接近戦でした。そこから抜け出すためには、課題曲を満遍なく再生する能力が要求されます。そこで問題になるのは「音楽表現力」です。課題曲3曲はそれぞれ異なる表情をもっています。それを十全に再現するためには、個々のCDを聴いて演奏家がそこで表現しようとしているものを「読み取る力」が要求されます。読み取ったものを音に反映する技術は、皆さん持ち合わせているから、たいせつなのは「読解力=読曲力」です。今回も気になったのは、音量の指定が適切な範囲から大きく逸脱しているクルマがあったことです。音量の指定にあたっては、自分だけで判断するのではなく、客観的に決定する配慮が欲しいですね。
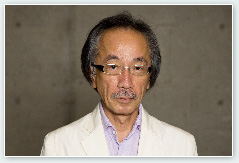
オーディオエンジニアに理想の音を尋ねれば、誰もが「色つけのない音、ナチュラルサウンド」と答えるでしょう。ところが彼らの造る音は100人100様です。なぜそんな違いが出るかといえば、あくまで「造った本人にとって色づけのない音」だからです。他の人が聴けば「個性」に感じられる。今年の参加車は、シャープで、タイトで、ブライトな音が多かった。これが、今回の参加者の多くが持っている個性でしょう。しかし、個性を認める前の段階で、バランスが悪いなどで脱落するクルマもありました。まず基本を押さえてください。周波数特性的に凹凸なくして欲しいし、スピード感も揃えて欲しい、ノイズレベルは下げて欲しい。それから個性を発揮してください。
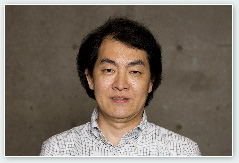
課題曲の「ジュピター」の難しさは、古楽器を使用した演奏スタイルをとっていることでしょう。弦楽器の音はちょっと細くてピッチが低く、木管楽器も現代の楽器とは構造が異なりますから、現代の楽器が聴かせてくれる厚みや柔らかさは出てこない。音質評価をするソースとしては、かなり厳しいものでしょう。しかし、楽器からの直接音と、会場の残響・余韻がブレンドされることによって、ちょうどよいバランスが得られる。その再現が難しいのですが、聴かせていただいたクルマは、ちょっとキツイ音が多かった。クルマではトゥイーターの距離が近いし、空間も狭いですから、音をブレンドさせることは難しいのですが、配慮していただきたいポイントです。
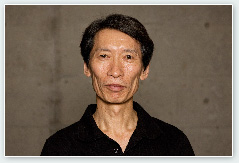
担当したクラスの実力は拮抗していて得点は非常に僅差でした。「内蔵アンプ」は、取り付けるクルマも小さくて剛性の弱いものも多いため、その難点を上手く克服したインストーラーがよい成績を収めました。指定音量が大きすぎたり、課題曲すべてを同じボリューム位置で聴くように指定したクルマも多かったですが、CD個々に最適な音量は異なるので、よりキメ細かな配慮が必要でしょう。「カーシアター」の参加車は粒ぞろいでしたが、特に1位と2位は、どちらが上でも不思議はない。映画のサウンドではダイアローグが特に重要で、また「ナマ音」の再現性によって、音のリアリティがまったく変わってくるので、チューニングの上では注意していただきたい。

エントリーシートは審査の上で重要です。課題曲3曲についてトータルのアピールポイントを要領よく、簡潔にまとめてください。審査員に訴えたいポイントと、実際に出ている音に整合性があるか否かも重要です。アピールポイントと実際に出ている音に齟齬がないようにしていただきたい。音場感、ステレオイメージを重要視する記入が多かったにもかかわらず、実際にクルマの中で鳴っていた音の印象は異なるものが多いのも気になりました。今年の「リファレンスカー」の音場感、ステレオイメージの再現を、参加者の皆さんも試聴、確認していただきたい。また、サブウーファーとフロントスピーカーの一体感にやや問題があるクルマが散見されたのも残念なことです。
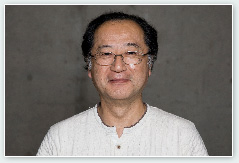
「基音」の再生を見直しましょう。たとえば、オーケストラ。バイオリンの輪郭を明確にしたいあまりに、中低域を細くしてしまうと基音が損なわれる。基音とは中低域の「下支え」です。ここが出ていないと、基音の音像ができない。基音がないと、薄っぺらな安手の音になってしまう。400Hzから1.2kHzくらいの音像をしっかり出せるか否かが、システムのポイントです。ここを見直すことで、大きく得点が向上するでしょう。シアターに関しては、方向感、定位感、包囲感をいかにして再現するかが重要です。センターとリア、フロントとリアのバランスetc.をすべて整えたとき、クルマの中にシアター空間が出来上がる。優勝車は見事に実現されていました。