|
|
|
「なんでお父さんの言うことには返事して、私の言うことには返事しないのよ!」と言うお母さんの怒りはごもっとも。でも、ちょっと待ってください。お爺ちゃんは本当に聴こえなかったのかもしれませんよ。
ヒトは年齢を重ねるに従って、いろいろな機能が低下します。もちろん、聴覚もです。
聴覚の場合、加齢により一般に高い周波数が聴こえにくくなってきます。これを老人性難聴と言います。これは長年いろいろな音を聴くことで、感度の高い周波数を聴く機能が老化してくるためです。
老人性難聴になると、会話に含まれている高周波数の子音が聴きとりにくくなるので、大きな低い声で、ゆっくり、はっきり話してあげることが大切です。このお母さんの場合、もしかしたら声が高くて、しかも早口でしゃべっていたのかもしれませんね。
同様に電子レンジやタイマーなどの家電製品の場合、ピッとか、ピピッというお知らせ音が聴こえないという現象もでてきます。これは従来のお知らせ音が、成人の聴域特性で最も感度の高い4000ヘルツ付近に設定されていたためです。最近では高齢者に配慮して、お知らせ音を2000ヘルツ付近の低い周波数とした家電製品も発表されています。
高齢者の転倒を防止するために、住まいの段差などをなくすバリアフリーが広まっていますが、これなどは音のバリアフリー、と言えます。
とはいえ、難聴はお年寄りだけのものではありません。長期間にわたって同じ音を聴きつづけていると、次第に騒音性難聴になる可能性もあります。また、ヘッドホンで音楽を楽しむ場合も、音量や使用時間に気をつけないと騒音性難聴になることがあります。騒音性難聴が進行すると、老人性難聴のように高い周波数が聴こえなくなったり、耳鳴りがしたりすることに。若いからと言って油断せずに、くれぐれもご注意を。
|
 |
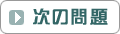 |
|
 |