|
|
|
夏になれば、あちらこちらで催される花火大会。すぐそばでドーンというお腹に響く音とともに見上げる花火もよいものですが、遠くからゆったり眺める花火もなかなかですよね。
さて、問題の答えですが、「音」は20℃のいわゆる常温で、毎秒340メートル伝播します。ですからこの場合、花火が開いてから聞こえるまで3秒かかったということは、 340×3=1020メートル程の距離があったことに。
ちなみに、音と違って光は、ご存じのように超高速。毎秒30万キロメートル進みます。これを月までの到達時間で比べてみると…(実際は宇宙空間では音は存在しないので、 あくまで目安としてのお話です)。地球から月までの距離は約384,400km。ですから、光なら約1秒ちょっとで月に到達します。では音の方はどうでしょうか。384,400÷0.34は、ええと、約1,130,588秒。ということは、約18,843分で、ということは、約314時間3分。ふぅ、ずいぶん違うものですね。
ではここで、音の性質に関してのお話を少し。
音には光と同様、反射、屈折、回折、干渉といった波動の性質があります。
例えば音は壁に反射して戻ってくる性質があり、山びこからもわかるように、光と異なり鏡面である必要はありません。また、空気中に温度変化や風速の変化があると、音はまっすぐ進まず曲がる屈折が起きます。昼と夜で遠くの音の聞こえ方が異なるのは、音環境の変化もありますが、屈折の影響が大きいのです。
さらに音は、塀などで音を遮っても、陰になる部分へ音が回り込む回折も起きます。音は光よりも波長が大きいので回折現象が現れやすく、特に低い周波数で顕著となります。 そして、干渉。音と音が重なることで、強めあったり弱めあったりする現象が起きます。 この干渉を有効に活用することで、不要な音を消すことも可能です。
いやはや、ひと口に音といっても、実は様々な動きをしているんですね。
|
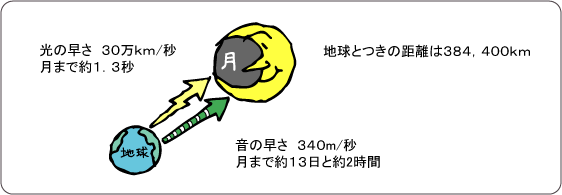 |
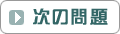 |
|
 |